

息子はイヤイヤ期が少しずつではありますが終わりつつあって、ぼくの前ではお利口さん、奥さんの前では甘えたがりという感じになってきました。つまり奥さんがいたら甘えてイヤイヤすることもあります。奥さんが「なんでだよ!」って言ってる。ほんとなんでだろうね…

しかし保育園に預けるとき、1個上のクラスとかでもイヤイヤしてる子はもちろんいるんですが、今朝その子に対してすっっっごい大声で叱ってる親御さんがいました。ダメです。めっちゃダメ。まずイヤイヤ期とかじゃなくて、そもそも人が見てる前で叱るのがダメ。てなわけでイヤイヤ期にやっちゃダメなタブーまとめました!
2歳のイヤイヤ期とは?基本を知ろう

イヤイヤ期はなぜ起こるのか?
2歳の子どもが「イヤ!」を連発する理由は、「自我の芽生え」によるものです。この時期、子どもは自分の意思を持ち始め、自分で選びたい、行動したいという欲求が強まります。しかし、それを上手に言葉や行動で表現するスキルがまだ未熟なため、イヤイヤで感情を伝えようとします。例えば、「自分で靴を履きたいけどうまくできない」といった状況で「イヤ!」となることがあります。親としては困る場面も多いですが、これは健全な成長の一部です。焦らず対応しましょう。
子どもの成長におけるイヤイヤ期の役割
イヤイヤ期は、子どもが自己主張を学ぶ大切な時期です。この時期に「イヤ!」と言える経験を通じて、自分の気持ちを理解し、周囲に伝える力を養っていきます。また、親に対して「こうしてほしい」と主張することで、自己肯定感も育まれます。一方で、この時期を通じて「他人の意見を尊重すること」も学びます。子どもにとっては大切な成長のプロセスであり、親としても見守りながら適切に対応することが求められます。
イヤイヤ期で絶対にやってはいけない5つのタブー

怒鳴りつけることの悪影響
イヤイヤ期の子どもに対して怒鳴りつけるのは逆効果です。感情をぶつけられると、子どもは恐怖を感じてしまい、親との信頼関係が損なわれます。また、怒鳴られることで、子どもが「自分の気持ちは無視される」と感じ、さらにイヤイヤがエスカレートすることもあります。大人が冷静に対応することで、子どもも安心して成長できます。一旦立ち止まって深呼吸し、落ち着いて対応しましょう。

うちはお風呂がいちばんイヤイヤでしたねー…なかなか入ろうとしてくれないんで、脱衣所から優しく声をかけてちょぉ~っとずつお風呂へ誘導するというのを毎日やってました。もちろん全裸。冬は寒かった…。
子どもの意見を無視すること
「どうせ子どもだから」と子どもの意見を無視するのはNGです。イヤイヤ期は、子どもが自分の意思を伝えようとする時期です。その意見を否定されると、自己肯定感が低下し、「自分の気持ちは大切ではない」と感じてしまいます。例えば、子どもが「これを着たい!」と言ったときは、「いいね!じゃあお外は少し寒いから上着を着ようね」と受け止めてあげると、子どもも納得しやすくなります。

ちなみに2歳は、大人が思っているよりも大人の言葉を理解しますよ!子供だからといって子供扱いしちゃだめってことですね。
大人の都合を押し付けること
時間がないときや忙しいときほど、つい子どもに「早くして!」とプレッシャーをかけてしまいます。しかし、これでは子どもが反発しやすくなります。例えば、朝の準備で「この靴を履いて!」と急かすよりも、「今日はどっちの靴を履きたい?」と選択肢を与えることで、自分で決めた感覚を持たせることができます。親も余裕を持って対応できるよう、時間に余裕を作る工夫が必要です。
物でごまかしてしまう対応
イヤイヤ期を乗り越えるために、おもちゃやお菓子で気をそらすこともあるかもしれませんが、これが常態化すると「イヤイヤをすれば得をする」と学んでしまいます。例えば、外出先で泣きわめく子どもにすぐお菓子を渡してしまうと、子どもはそれを要求する行動を繰り返す可能性があります。まずは子どもの気持ちを受け止め、「どうしてイヤだったの?」と気持ちを言葉にする練習を促すことが大切です。
子どもの感情を否定する言葉かけ
「泣かないの!」や「そんなことで怒らないで」といった否定的な言葉は、子どもの感情を押しつぶしてしまいます。子どもにとっては、どんな小さなことでも大きな問題に感じるものです。まずは「そう感じたんだね」「それは嫌だったね」と共感してあげることで、子どもも安心して気持ちを伝えられるようになります。否定ではなく、受容の姿勢を心がけましょう。
シチュエーション別!イヤイヤ期でやってはいけない対応
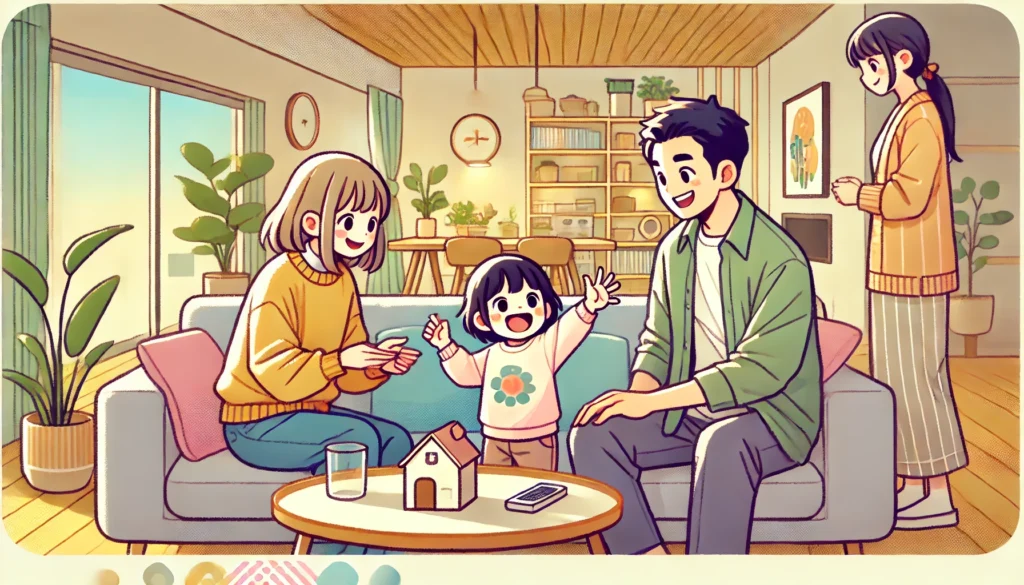
食事の時間:無理やり食べさせるのはNG
子どもが食事を嫌がるとき、無理やり食べさせるのは逆効果です。無理に口に入れようとすると、食事そのものが嫌いになる可能性があります。例えば、好きなキャラクターのプレートを使ったり、小さなおにぎりを一緒に作るなど、楽しい雰囲気を作ることで食事への興味を引き出しましょう。また、「食べなくてもいいよ」と余裕を見せると、逆に子どもが自然と食べ始めることもあります。
お風呂の時間:泣き叫ぶ子に無理強いしないコツ
お風呂を嫌がる子には、無理に入れようとすると余計に嫌がります。例えば、お気に入りのおもちゃを持ち込んで「お風呂で遊ぼう!」と誘ったり、好きな泡立ちグッズを使ってみるのも効果的です。また、「お湯が気持ちいいね」と声をかけながら、子どもがリラックスできる雰囲気を作ることが大切です。
外出時のイヤイヤ:時間に追われてイライラしない方法
外出時にイヤイヤをされると、親はついイライラしがちです。しかし、子どもは「自分で決めたい」という気持ちが強い時期です。例えば、「今日はこの服にしようね」と決めつけるのではなく、「赤い服と青い服、どっちがいい?」と選ばせることで、スムーズに進むことがあります。時間に余裕を持つスケジュール管理も重要です。
寝かしつけ:焦ってプレッシャーを与えない工夫
寝る時間になっても子どもがなかなか寝ない場合、「早く寝て!」と焦ると、子どもは余計にプレッシャーを感じます。代わりに、「一緒に絵本を読もう」「おやすみなさいの歌を歌おう」といったリラックスできるアプローチが効果的です。また、寝室の明るさを調整したり、静かな環境を整えることで、自然と眠気がくるようにしましょう。
イヤイヤ期を乗り切るために親ができること

子どもの気持ちを受け止める具体的な方法
イヤイヤ期の子どもが「イヤ!」と言ったとき、親としてはつい「そんなこと言わないで!」と思ってしまいがちです。しかし、まずはその気持ちを受け止めることが大切。例えば、子どもが着替えを嫌がった場合、「この服を着たくないんだね」と共感を示すだけで、子どもは「自分の気持ちを分かってくれた」と感じます。その上で、「じゃあ、この服とあの服どっちがいい?」と選択肢を与えると、スムーズに行動に移ることができます。子どもがイヤイヤを通じて主張している感情に耳を傾けることが、親子の信頼関係を深める鍵です。
親自身のストレスケアの大切さ
イヤイヤ期の対応は、親にとっても精神的に負担がかかる時期です。特に1日中イヤイヤが続くと、どうしても疲れてしまいます。このようなときには、親自身のストレスケアが必要です。例えば、子どもが寝た後にリラックスできる時間を作ったり、パートナーや信頼できる人に育児の悩みを相談することも効果的です。また、「今日は頑張った」と自分を褒める習慣をつけるのもおすすめです。親が元気でいることで、子どもにも穏やかな対応ができるようになります。
家庭内で協力するためのコミュニケーション術
イヤイヤ期を乗り切るためには、家庭内での協力体制が欠かせません。例えば、パートナーと育児の負担を分担することで、親自身の負担を軽減することができます。育児の進捗や悩みを共有するために、週に1度でも「育児会議」を設けると、スムーズにコミュニケーションが取れるようになります。また、家族全員で「子どもを見守る」姿勢を持つことで、子どもも安心感を得られるようになります。
まとめ:イヤイヤ期をポジティブに乗り切ろう

イヤイヤ期は親にとっても試練の時期ですが、同時に子どもの成長を感じられる大切な時期でもあります。親子で一緒に乗り越える経験が、信頼関係を深めるきっかけとなります。「イヤイヤ」に振り回されるのではなく、成長の一環と捉えてポジティブに対応しましょう。この時期を乗り越えた先には、子どもとの絆がより強くなった自分が待っているはずです。

様々なアドバイスありましたが、無理にこれを全てやろうとするのも大変ですし、むしろ疲れちゃいます!人間ですから気持ちをコントロールするのなんてそう簡単にはいきませんもんね。できる範囲からやっていきましょ!



